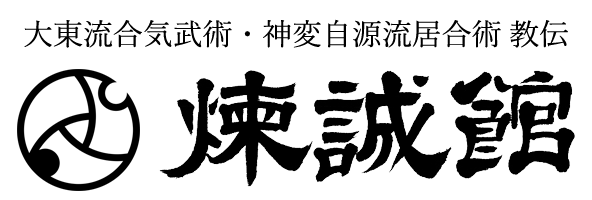稽古の方針
同じ気持ちを持つ仲間と共に
みなが心地よく稽古するための環境
煉誠館の稽古では、剣術、柔術、杖術などを通じて、武技の修得や心の向上を目指します。
ただ、闇雲に反復練習をすれば上達するというものではありません。一つひとつの動きを大切にして、自分自身の身体と心を観察しつつ、相手との関係性を構築する。その努力の積み重ねが、上達への道標となります。いくら数多く繰り返しても、間違ったやり方では逆効果です。
具体的には、我(仕太刀)と敵(打太刀)に分かれて決まった動きを行う「型」によって、自分自身と向き合います。格闘技や一部の武道のような激しい組手を行うことはありませんので、年齢や性別を問わず、誰もが安全に学ぶことが可能です。もちろん武術ですから、極端なことをすれば怪我の可能性もありますが、安全には十分に配慮して稽古しております。
他の古流武術がそうであるように、煉誠館においても表面的な筋力を否定するため、過度の筋力トレーニング等も行いません。
木刀の素振りなどを行えば自然と筋肉を鍛えることになりますが、それは副次的なものです(ただし、正しい方法論で身体を鍛えることは否定しません)。
初心の段階では、筋力を用いた動きをひたすら制限し、武術的な思考を心身に馴染ませることを目指します。
また、いわゆる体育会系のノリで根性を身につけようとしたり、上位者が横柄な態度をとることもありません。一部の道場で未だに見受けられるそのような風習は非常に恥ずべきものであり、百害あって一利なしです。道場とはいえ社会の一部なのですから、一般社会で通用しないことを押し通すことはありません。
武術修行の大きな課題として礼節というものがあり、みなが気持よく稽古に励めるよう最低限の礼儀やマナーを守りつつ、良い雰囲気で活動したいと考えております。