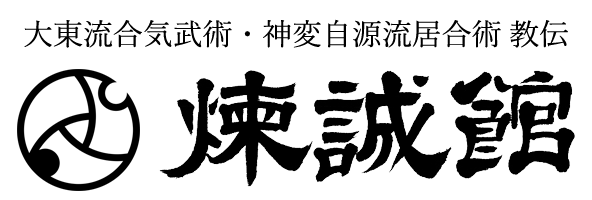柔術
武士が素手の時に用いる、剣の裏技
柔術の概略
柔術は、武士が剣を抜かない時に用いる素手の技術です。敵の力を利用して関節を攻め、当て身を打ち据え、投げ放つ。技量が勝っていれば、相手を傷つけることなく制御して場を収めることができる、平和を体現する技術でもあります。
素手で敵を制するというイメージが先行して、剣とは何の関係もない独立した技術であると思われがちですが、身体の使い方や足捌きなどは剣術のそれと同じであるため、柔術を理解するためには、剣術への理解を深めることが不可欠となります。
特に、煉誠館に伝わる柔術は、会津藩・御式内を母胎とする総合武術「大東流」の技を主軸としているため、「柔術は素手の技にあらず、剣を持たない剣術であり、剣の裏技である」という口伝を忘れることなく研鑽を積んでおります。
柔術において最も大切なことは、敵を制御して攻め入らせないようにする、ということです。敵の中心を感じ取り、力を出せないような状態に導いた後に技に入るのです。
普段の稽古で学ぶ型は、関節の極め方、投げ方などを中心に編まれております。そのため、関節技や投げ技が柔術だと考えている人が多いのですが、それらは枝葉の部分であり、本質ではありません。技に入る前に敵を制御して力を削いでおかなければ、逆に抵抗されて反撃を受けてしまいます。
敵をしっかりと制御して自由を奪うからこそ技が掛かるのであり、その制御部の理論こそが柔術の枢要です。
型で学んだ技を実用に耐えうる技にするためには、この制御法(崩し)を、よくよく研究しなくてはなりません。例を挙げるならば、タイミングを計らって押し引きをする、当て身で意識を弾く、力貫で敵の重心を狂わせる、などの方法論がありますが、煉誠館として最重視するのは「力貫」での崩しです。
即効性のある護身術としては当て身が有用で、敵が抵抗した際には、これを用いて敵の意識を逸らします。初心の段階では、力貫の術を駆使することは非常に困難ですから、ある程度の術が身につくまでは、敵が崩れるまで繰り返し当て身を打ち据えて、力貫の代替とするのです。
しかしながら、いつまでも当て身に頼るのは良くありません。当て身は、効果を求めれば求めるほど敵を傷つけてしまい、場合によっては死に至らしめる危険性もあります。柔術の理想型は、敵も自分も傷つかずに場を収めることです。そのために、煉誠館では力貫による崩しに柔術の精髄を求めます。
最初は敵を徹底的に痛めつけて制圧する狂気の技術であったものが、やがて、自他を傷つけない平和の境地へと昇華する。その変転の中に、柔術の崇高な理があると考えています。
-

柔術の稽古風景
-

四方投げ
-

あくまでも剣であり、剣の利で動く
柔術教伝内容
手解き
- 基礎の体捌き
- 基礎の当身
- 手解きの柔術 三本
- 股割り
初伝儀
- 初伝技法
- 【教外別伝】
- 護身試合口 五本
中伝儀
- 中伝技法
- 【教外別伝】
- 護身試合口 九本
- 当身素振り
奥伝儀
- 奥伝技法
※口伝、教外別伝、秘伝あり